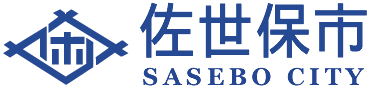「消防・防災」の検索結果55件
部局/課検索
検索結果
-
佐世保市消防局では NET119 をご利用いただける方を『聴覚や発語に障がいがあり、音声による119番通報が困難な方』としております。 救急車の要請を例に出すと、電話による119番通報では、通報者と消防職員が会話によって「救急車が向かう場所」「現在の状況(症状)」等を聴取しますが、聴覚や発語に障がいをお持ちの通報者と電話でコミュニケーションをとることは非常に困難です。 NET119は聴覚などに障がいをお持ちの方でも119番通報が行えるように開発されたサービスで、簡単...
消防局 - 指令課
-
119番通報を間違ってかけた場合は、「間違えました」とひと言伝えた上で電話をお切りください。 119番通報があり電話に応答がない場合、通報された方が電話口で倒れて応答できないのかもしれないという最悪の事態を想定し、消防局では救急車を出動させるようにしています。 通報された方の安全が確認できれば救急車を出動させることはありませんので、間違って119番通報してしまった場合は、安全確認の意味も含め、慌てて電話を切るのではなく「間違えました」と伝えるようにしてくださ...
消防局 - 指令課
-
携行品は多すぎると避難に支障がでるばかりか、周りの人に迷惑がかかることもありますので必要最小限にとどめましょう。 リュックなどに入れられる範囲で、代表的なものは、 水(ペットボトル) 食品(缶詰のご飯など)2~3食分 雨具や防寒衣 下着類 懐中電灯 洗面用具 ちり紙、タオル 箸、スプーン 缶切りなど小道具類 救急薬品、用具、常備薬 貴重品 などです。 そのほか、生活習慣において必要なものは各自用意しましょう。
防災危機管理局 -
-
佐世保市防災情報メールとは、防災行政無線で放送された内容を電子メールで配信するサービスです。 防災行政無線が「聞こえづらい」や「何を言っているのかわからない」等の場合に、お手持ちのスマートフォンやパソコンなどで放送内容を文字で確認していただくことができます。 詳しくは下記佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ【佐世保市防災情報メールについて】
防災危機管理局 -
-
長崎県が指定した土砂災害のおそれがある区域について、土砂災害ハザードマップ(避難地図)を順次作成しています。 急峻な山や斜面が、住宅地背後に位置するような地域では、がけ崩れや土石流といった自然現象により、土砂災害が発生するおそれがあります。 土砂災害ハザードマップは、土砂災害に関する情報を、住民の皆様へお知らせすることにより、人的被害を最小限にとどめることを目的としています。 土砂災害ハザードマップには、土砂災害のおそれがある区域や土砂災害時の避難所、気象情報...
土木部 - 河川課
-
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)により指定された、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域です。 「土砂災害警戒区域」は、土砂災害により住民の生命又は身体に危害が生じるおそれのある区域のことです。 「土砂災害特別警戒区域」は、土砂災害により建築物に損壊が生じて住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある区域のことです。 この区域内の開発行為に制限があり、居室を有する建築物の構造にも規制があります。 詳しくは...
土木部 - 河川課
-
土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、 土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにする。 当該区域における警戒避難体制の整備を図る。 一定の開発行為を制限する。 建築物の構造規制をする。 こと等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。 いわゆる施設整備によるハード対策ではなく、ソフト対策と考えられています。 指定区域には「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別警戒区...
土木部 - 河川課
-
佐世保市では、防災行政無線の放送内容を以下の方法で確認することができます。 (1)佐世保市のホームページ > 防災行政無線の放送内容 佐世保市ホームページに放送内容を掲載しています。 掲載場所:https://www.city.sasebo.lg.jp/bousaimusen/index.html (2)佐世保市防災情報メール 放送内容を電子メールで配信します。(メールアドレスの登録が必要です) 登録方法:https://www.city.sasebo....
防災危機管理局 -
-
記載事項(本籍や氏名など)に変更がある場合や、免状の交付(再交付を含む)を受けて10年を経過している方は書換えの申請をしなければなりません。 書換えの申請書はお近くの消防署・出張所に配置しています。
消防局 - 予防課
-
急傾斜地崩壊危険区域に指定されると、人命保守の目的から行政が関係者に代わり急傾斜地(自然斜面)の崩壊対策事業(工事)を実施することができます。 指定の条件は、高さ5m以上、被害想定家屋5戸以上、斜面の傾斜度30°以上の急傾斜地(自然斜面)となっています。 指定を受けると当該急傾斜地の崩壊を誘発したり助長すると考えられる行為に制限が課せられます。 制限行為につきましては、詳しくは県北振興局 建設部 砂防防災課にてご確認ください。
土木部 - 河川課
-
土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所については長崎県が調査を行っております。 電話等での回答は要望箇所の正確な把握できない場合がありますので、当該地が危険か否かを確認したい場合は県北振興局建設部砂防防災課および佐世保市土木部河川課にお越しください。
土木部 - 河川課
-
FAQ
心臓突然死の多くの場合は、心筋梗塞などで心臓が突然けいれんした状態で、心臓が本来持っている全身に血液を送り出すポンプとして機能を果たすことができなくなります。AEDは電気ショックを与えて心臓のけいれんを止め、心臓を本来の動きに戻すための医療機器です。 AEDの使い方は、消防署が実施する救命講習で学ぶことができます。 また、佐世保市消防局では中央消防署・東消防署・西消防署に1台づつイベント等で使用できる貸し出し用のAEDがありますので、お近くの消防署へお尋ね...
消防局 - 警防課
-
危険物取扱者試験((財)消防試験研究センター主催)は、長崎県内では年2回(例年6月と11月に)実施されています。 日程につきましては、(財)消防試験研究センター(http://www.shoubo-shiken.or.jp/)をご参照ください。 詳しくは、(財)消防試験研究センター長崎県支部(電話番号095-822-5999)または消防局予防課(電話番号0956-23-9257)までお問い合わせください。
消防局 - 予防課
-
消防設備士試験は(財)消防試験研究センターで行っています。 詳細は(財)消防試験研究センターのホームページをご覧下さい。 なお、長崎県の場合、例年受付が6月中旬から7月初旬、試験が8月中旬に行われる予定です。 また、電子申請の受付も行われております。
消防局 - 予防課
-
危険物の取扱い作業に従事する危険物取扱者は、従事することとなった日から1年以内に、その後は3年以内ごとに長崎県知事が行う講習を受けなければなりません。 長崎県内での危険物取扱い講習は、(社)長崎県危険物安全協会が指定機関として例年9月に実施しています。 詳細については、(社)長崎県危険物安全協会(電話番号095-827-8479)または消防局予防課(電話番号0956-23-9257)へお問い合わせ下さい。
消防局 - 予防課
-
住宅用火災警報器は、就寝中の逃げ遅れを無くすことが主たる目的ですので、寝室に設置する必要があります。 また、2階建ての場合に寝室が2階にある住宅は、2階の階段部分にも必要です。 その他ご不明な点は消防局予防課までご連絡下さい。
消防局 - 予防課